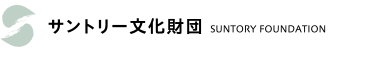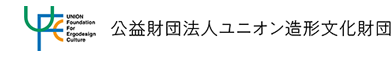第6号
特集:
戦時下の生環境──クリティカルな生存の場所 Wartime Habitat: A Critical Place of Survival 战时生环境──临界性的生存场所
戦時下生環境ガイド[4]平原──塹壕と平地、第一次世界大戦を中心に
藤原辰史【HBH同人】
Guide to the Wartime Environment [4] Trenches and Plains: Focusing on World War ITatsushi Fujuhara【HBH editor】
戰时生環境導覽[4]戰壕和平地──以第一次世界大戰為中心
One of the most unique features of World War I was that the Western Front was trench warfare. Trenches were structures made of holes dug to avoid bullets and shells in plain battle, reinforced with sandbags and timber, and boarded up at the foot of the trenches. New weapons such as poison gas and tanks were introduced to break the stalemate of trench warfare. In addition, a number of young soldiers became mentally ill in the closed spaces, a condition known as “shell shock”. This article will consider the meaning of this construct, which is important in examining the relationship between the military and the environment.
[2023.6.10 UPDATE]
第一次世界大戦の特徴として、西部戦線が塹壕戦だったことが挙げられる。塹壕とは、平地の戦闘で銃弾や砲弾を避けるために掘った穴を、土嚢や木材で補強し、足元に板を敷いた構築物である。膠着状態に陥る塹壕戦を打破するために、毒ガスや戦車のような新兵器が登場した。また、閉鎖空間の中で精神を病む若い兵士が続出し、その症は「Shell shock」と呼ばれた。本稿では、軍事と環境の関係を考える上で重要な、この構築物の意味を考えてみたい。
はじめに
2022年2月24日、ロシアによるウクライナでの「特別軍事作戦」が始まって以来、その領土内で軍事衝突が繰り広げられている戦地には、長距離にわたって塹壕が掘られているところもある。前線のドネツク州バフムートでも首都キーウでも、第一次世界大戦を彷彿させる、まさに「前世紀の遺物」が、若いウクライナ兵たちをロシア軍からの攻撃から守る切実な構築物としてニュース映像に繰り返し映されている。そこでは、これまた百年前と同様に、兵士はキーンという金切音とともに高速で飛んでくる砲弾の音に耳を抑えつつしゃがむ。こうやって、鼓膜が破れたり、上半身のどこかが銃弾で抉られたりするのを防ぐ、という身振りも百年前と変わらない。サイバー攻撃や無人機の攻撃が多用されている現代戦争においても、塹壕がこれほどまでに存在感をしめしていることについては繰り返し言及されてきた。重要なのは、ウクライナはドニプロ川を挟んで東側はほとんどが平原であることだ。身を隠すのに都合の良いのは起伏の飛んだ場所だが、平原では、双眼鏡があれば遠くの敵陣から確認しやすくなるのでそうはいかない。どれほどサイバー空間が充実しようが、この地形で戦争が勃発すれば、地面に穴を掘って隠れるしかないのである。
塹壕とは何か
塹壕とは、比較的平らな土地での戦闘で、敵の銃弾による攻撃から身を守るために、人力もしくは機械の力によって掘られた溝のことである。塹壕をしばらく歩いていくと、屋根があって、その奥には将校の部屋、病人を一時的に治療する病室、倉庫などが設営されていることも多い。地球の表土に刻まれた溝であるとともに、トンネルでもある。1914年夏から1918年秋まで足かけ5年にかけてヨーロッパ大陸を主戦場として繰り広げられた第一次世界大戦で、同盟国のドイツから見て西部戦線には過去最長の規模で塹壕が掘られた。1914年の11月から12月に、北はベルギーの北海沿岸から、フランスとスイスの国境までおよそ800kmに両陣営の塹壕が対峙したのである★1。なぜなら、第一次世界大戦は、これまでアメリカの南北戦争、アフリカでのヨーロッパ支配に対する蜂起の鎮圧、日露戦争などで使用された機関銃が、自国の膨大な銃弾や砲弾生産を背景に、かつてない量が使用され、文字通り鉛の嵐の中での戦争が強いられたからである。ちなみに、1914年9月のマルヌの戦いだけで、独仏両軍で日露戦争に匹敵するほどの弾薬が消費されている。
さらに、低湿地の戦場ではぬかるみ、兵士や馬の足がはまりやすく、敵軍の進行を防ぐために有刺鉄線が張り巡らされたこともあり、戦線は膠着状態に陥る。数キロ、場合によっては数メートル前進するたびに、数千人の規模の兵士の命が失われた。シュマン・デ・ダムやパッシェンデールなどの高地をどう奪うかが、平地戦で重要だった。
ランゲマルク近くにあるコモンウェルス戦争墓地委員会が管理するタイン・コット墓地に訪れれば[fig. 1]、第一次世界大戦で亡くなった兵士たちの墓だけではなく、ピラーボックス(銃を撃つことのできる小さな穴が空いたコンクリートの建築物)やコンクリートのシェルターの残骸も残っている。ちょうどこの墓地に立つと、田園風景が緩やかに下った斜面に広がっていることがわかる。要するに、墓地が存在したところは高地に存在し、両軍にとって戦略上の要所であった。

fig. 1──管理の行き届いたタイン・コットの墓地
引用出典=Wikipedia Commons(Photo by Thomas Hanmer)
塹壕戦を打開するための毒ガス
このような状況を打破するために投入されたものが、膨大な砲弾の嵐と、塩素ガスという毒ガスであった。1899年のハーグ陸戦条約で禁止されていたにもかかわらず毒ガスを戦場で初めて使ったのはドイツ軍で、1915年4月22日、ベルギーのイープルのことである。連合軍に5,000人ほどの死者が出た。風向きさえ読むことができれば、毒ガスは地形にかかわらず敵兵の戦闘能力を奪うことができる。1916年2月にはヴェルダンでフランス軍がフォスゲンというさらに殺傷能力の高い毒ガスを用いて、ドイツ兵を苦しめた。各国とも、人間のみならず、犬や馬などの動物兵士にもガスマスクをつけて、毒ガスによる死を防ごうとした。だが、1917年7月21日には、ドイツ軍は、ガスマスクでは対応できない毒ガスを使用する。マスタードガス(別名イペリット)である。ほのかにマスタードの香りがすることからこの名前がつけられたのだが、衣服を浸透して皮膚をただれさせるものだった。フォスゲンよりも致死率は低いが、人間の体の中で最も痛みを感じる部位である皮膚と真皮を攻撃した上に皮膚呼吸を困難にさせるので、十分残虐な兵器であった。
塹壕を襲ったのは、毒ガスだけではない。戦車が開発されたことで、不整地でも前進できるようになり、塹壕に身を隠す兵士を踏みにじった。さらに、毒ガスが襲ってきたり、砲弾が落ちたりしなくとも塹壕はそれだけでも兵士たちにとって危険な構築物であった。
第一に、ぬかるむ塹壕はスノコが敷かれ、少しでも通気性をよくしようと試みられたが、ネズミが縦横に走り、病原菌も蔓延しやすい状態にあることに代わりはなかった。チフスやコレラ、あるいは塹壕熱と呼ばれた原因不明の感染症に罹患しないために、制服の燻蒸や殺虫剤の使用によって媒介昆虫の除去が試みられたが、完全に防ぎ切ることはできなかった。燻蒸のためには除虫菊が使用されたが、戦時中日本(主産地は徳島)からヨーロッパへの除虫菊の輸出量は、開戦まえの三倍に達した★2。
毒ガスが初めて使用されたイープルには博物館や塹壕の跡、塹壕を復元したものが点在する。例えば、第三次イープル戦(パッシェンデールの戦い[fig. 2])の跡地には、レプリカの塹壕やオリジナルの塹壕がある。そこを歩くと、塹壕が木や土を素材に不安定なかたちで組み立てた(当然のことだが)仮住まいの建築物であることがよくわかる。

fig. 2──パッシェンデールの戦いの時の塹壕
引用出典=Wikipedia Commons(Photo by Thomas Hanmer)
ドイツ軍は、ソンム川の戦いのおり、縦10mほどの深さの待避壕を建造した。イギリス側はこれを「鉱山式」と呼んだのだが、そのとおり、ドイツは鉱業の技術を用いて掘ったのだった★3。イギリスの戦史家のジョン・キーガンは、毒ガスを交えた砲弾をこの堅牢な待避壕に大量に打ち込んだにもかかわらず、ドイツ軍は持久戦を戦い抜き、イギリス軍を悩ませたと述べている。
砲弾ショック
塹壕戦が攻撃したのは、人間の身体だけではない。内面も大いに傷を受けた。「砲弾(シェル)ショック」と言われる精神の症状が兵士のあいだに広く見られるようになったのも、第一次世界大戦であった。掘った塹壕の中で、敵陣から撃ち込まれてくる無数の砲弾の音や衝撃波をくらっているうちに精神が参ってしまう。心が病んだ兵士は、自殺を試みるものもいた。第二次世界大戦時でも多くの日本兵士が精神の病に陥り、ヒロポンが流行したことをここで思い起こしてもよい★4。ところで、第一次世界大戦を精神医学の動員という観点から論じた上尾真道は、次のように述べている。「膠着した西部戦線において繰り広げられた塹壕戦は、泥まみれになりながら相手方に砲弾を撃ち込む持久戦であった。その疲弊した体を、近距離で破裂する砲弾の爆風に晒され、時に塹壕に生き埋めにされたのちに生還した兵士たちのうちには、明らかな外傷が見当たらないのにもかかわらず、痙攣、歩行困難、失明、失語、記憶喪失などの症状をきたす者たちが現れた」★5。
ところが、上尾によると、これほどの深刻な「砲弾ショック」が、次第に「戦争ヒステリー」として戦時の精神医学によって扱われるようになる。「詐病」として疑われる場合も、そうでない場合でも、精神医学は、患者をいかに治療し、再教育して、戦場に戻すか、という国家が要請する方向性にシフトしていった。
戦争は兵士の精神を破壊する。だが、それだけではない。精神を治療する医学もまた、兵士たちを追い込んでいくのである。
ヴェルダン要塞
1916年2月19日から12月9日まで繰り広げられたヴェルダン要塞の戦いは、両軍を足し合わせると70万人の死傷者を出したと言われている。ヴェルダンの跡地は、現在、フランス兵を中心とする連合国軍兵士の追悼施設と膨大な数の十字架の墓があり、さらにムスリム兵士の蒲鉾型の墓がメッカを向いている。フランスの植民地だったアルジェリアからも多数の兵士がヨーロッパにわたって戦死したからである。植民地からやってきた兵士がヨーロッパ大陸で戦ったり、アフリカ大陸で現地の兵士やヨーロッパの兵士が戦ったりしたのも、第一次世界大戦が「世界大戦」である所以である。
ヴェルダン要塞に訪れてまず驚くのは、現在もなお要塞の屋根の部分のいたるところに砲弾のクレーター跡があり、そこに植物が生えていること。どれほど激しい砲弾の嵐が降り注いだのか、変形した地形を見ることだけでも伝わってくる。環状分派堡という形式の強固な要塞であるが、その内部は現在も見学することができる。
ヴェルダン要塞に向かう途中、森の中を通るのだが、注意深く目を凝らすと、うねっている地面の上に植物が育っていることがわかる。どれほどの砲弾と銃弾を大地は吸収したのだろうか。
おわりに
ここでは、第一次世界大戦を中心に、塹壕と平地について論じた。塹壕は、ドイツでは、「塹壕社会主義」というように、文字通り同じ構築物の中で生活を共にするので、まがりなりにも普段感じ取ることのできない人びとの平等感を勝ち取ることができたが、他方で、塹壕は、身体と精神をすり減らす場所であり、その辛い経験を戦後まで引きずり、家族と打ち解けられなかった兵士も多かった。ヨーロッパ各地にある第一次世界大戦の塹壕跡や潜没兵士の墓は、当時のみならず、ウクライナの塹壕戦の苛烈さを喚起させる。注
★1──小関隆+平野千果子「ヨーロッパ戦線と世界への波及」(『現代の起点 第一次世界大戦1 世界戦争』岩波書店、2014、38頁)
★2──瀬戸口明久「空間を充たすテクノロジー」(『現代の起点 第一次世界大戦2 総力戦』岩波書店、2014、213頁)
★3──ジョン・キーガン『戦場の素顔──アジャンクール、ワーテルロー、ソンム川の戦い』(高橋均訳、中央公論新社、370頁)
★4──吉田裕『日本軍兵士──アジア・太平洋戦争の現実』(中公新書、2017)
★5──上尾真道「こころの動員──包摂装置としての戦争精神医学」(『現代の起点 第一次世界大戦2 総力戦』岩波書店、2014、192頁)
ふじはら・たつし
1976年生まれ。食と農の現代史。京都大学人文科学研究所准教授。著書=『ナチスのキッチン──「食べること」の環境史』(水声社、2012)、『トラクターの世界史──人類の歴史を変えた「鉄の馬」たち』(中央公論新社、2017)、『戦争と農業』(集英社インターナショナル、2017)、『給食の歴史』(岩波新書、2018)、『分解の哲学──腐敗と発酵をめぐる思考』(青土社、2019)など。編著=『第一次世界大戦を考える』(共和国、2016)など。共訳書=フランク・ユーケッター『ドイツ環境史 エコロジー時代への途上で』(昭和堂、2014)など。
- 生環境を捉える軍事史の系譜
-
The Bio-environment of the Battlefield from a Military Historical Perspective
/生環境視角下的軍事史譜系
唐澤靖彦/Yasuhiko Karasawa - 戦時下生環境ガイド[1]島──閉ざされた領域で継続する戦争
-
Guide to the Wartime Environment [1] Island: Sustained Warfare in a Confined Territory
/戰时生環境導覽[1]島──在封闭地区持续的战争
青井哲人/Akihito Aoi - 戦時下生環境ガイド[2]穴──沖縄戦とガマ
-
Guide to the Wartime Environment [2] Caves: The Battle of Okinawa and ‘Gama’(Karst)
/戰时生環境導覽[2]洞穴──沖繩島戰役和石灰岩洞穴
青井哲人/Akihito Aoi - 戦時下生環境ガイド[3]崖──ガリポリの崖、クルクキリセの高地
-
Guide to the Wartime Environment [3] Cliffs of Gallipoli, Hills of Kirk-Kilise
/戰时生環境導覽[3]崖──加里波利的懸崖,克爾克拉雷利的高地
伊藤順二/Junju Ito - 戦時下生環境ガイド[4]平原──塹壕と平地、第一次世界大戦を中心に
-
Guide to the Wartime Environment [4] Trenches and Plains: Focusing on World War I
/戰时生環境導覽[4]戰壕和平地──以第一次世界大戰為中心
藤原辰史/Tatsushi Fujuhara - 戦時下生環境ガイド[5]工場──封鎖による生存条件の損害
-
Guide to the Wartime Environment [5] Factory: Damage to Survival Conditions Due to Blockade
/戰时生環境導覽[5]工廠──封鎖對生存條件的損害
藤原辰史/Tatsushi Fujuhara - 論点[1]インタビュー:戦争と性
-
Issue [1] Interview: War and Gender
/論點[1]採訪──戰爭與性
奈倉有里/Yuri Nagura - 論点[2]原爆の遺品が語るもの──石内都『Fromひろしま』からの思考
-
Issue [2] What A-Bomb Mementos Tell Us: Thoughts from Miyako Ishiuchi’s “From Hiroshima”
/論點[2]講述原子彈的遺物──由石內都的《From廣島》引發的思考
藤原辰史/Tatsushi Fujuhara - 論点[3]工兵論
-
Issue [3] On Military Engineers
/論點[3]工兵論
唐澤靖彦/Yasuhiko Karasawa - 文献紹介[1]生環境としての戦場
-
Bibliography [1] Books on Battlefield as Habitat
/文獻介紹[1]戰場中的生環境
HBH同人/HBH editors - 文献紹介[2]軍事をめぐる写真集・図集
-
Bibliography [2] Photographic Collections and Illustrated Books
/文獻介紹[2]軍事寫真集・圖集
HBH同人/HBH editors - 文献紹介[3]戦跡のデザインあるいはキュレーション
-
Bibliography [3] Design of Battlefield (Museum on Violence)
/文獻介紹[3]關於戰爭遺蹟的設計或策展
HBH同人/HBH editor
協賛/SUPPORT サントリー文化財団(2020年度)、一般財団法人窓研究所 WINDOW RESEARCH INSTITUTE(2019〜2021年度)、公益財団法人ユニオン造形財団(2022年度〜)